こんにちは。記事を開いていただきありがとうございます。よしハムコロリと申します。
私は熊本でITエンジニアを25年以上行っています。主な役割はプログラマーが多いですが、プロジェクトリーダーや管理職の経験も有り、部下や後輩を教育する機会がありました。中堅のITエンジニアは、現場の即戦力であると同時に、次世代の人材を育てる重要な役割を担います。後輩の成長スピードは、指導内容によって大きく変わります。本記事では、私の経験が基になってしまいますが、中堅のITエンジニアが後輩を育成する上で考慮するポイントを書いてみたいと思います。
尚、本記事にはアフィリエイト広告を掲載しております。ご興味ありましたら、是非ご利用ください。
信頼関係の構築
1対1のコミュニケーションを重視
部下や後輩が話しやすい環境を設けたいと思い、2週間に1回くらいの頻度で1対1のミーティングを設け、困っていることや学びたいことを聞くようにしました。逆に、こちらから褒めたい点や注意してほしい点などを伝える場にもしました。
頻度は最終的には1ヶ月に1回くらいにしました。必ず話せる場としては非常に有用なのですが、毎回、同じ様な内容になったりすることがあったので、そのあたりの工夫が必要になることもあります。
失敗を許容する文化づくり
私の経験談になりますが、先輩の立場としては「自分ができる事」である為、後輩の失敗について「なぜできないの?」と追及してしまうことがありました。しかし、追い込んでも部下、後輩は委縮するだけで効果はほとんどありませんでした。失敗を責めるのではなく、逆に成長のチャンスとして活かすことが必要かなと思います。追及ではなく、失敗をリカバリーする方法と次繰り返さない為の方法を話し合うようにしたことがあります。上司、先輩としては、部下、後輩の失敗をフォローできるだけの余裕が持てていたら良いですね。
スキルの体系的伝授
技術とプロセスの両輪で指導
私は話が長くなってしまうのが悪いところなのですが、「なぜこの作業や過程が必要なのか」を説明することが多いです。本質を理解してもらってから作業に取り組んでもらう方が成果は上がりやすいと思います。このあたりを体系的に説明できるという点で私にとって役に立ったと思うのは、IPAの応用情報技術者試験の勉強をして資格を取得したことでした。幅広く知識を得ることができ、説明の内容に深みが増したと思います。
応用情報技術者試験についてはこちら↓
応用情報技術者試験のお話|熊本のITエンジニアよしハムコロリの資格試験
実務を通じた学び
どちらかと言うと、私は「自分がやった方が早い」と任せることができないでいました。でも、それでは部下、後輩はいつまで経ってもできるようになりません。簡単な作業や、全体の一部だけを実施してもらい、少しずつその範囲を広げていけば良いと思います。広げてからすぐにできない場合は、様子を見ながらしてあげると良いでしょう。あと、なぜこの作業が必要なのかという理由を教えてあげると良いと思います。
成長を促すフィードバック
タイムリーなフィードバック
フィードバック(行動や結果に対して、改善や成長を促すために、評価や意見を伝えること)は、作業直後やプロジェクト終了直後に伝えた方が良いです。「釘は熱いうちに打て」です。遅れてしまうと記憶やそのときの熱量は徐々に少なくなっていきますし、何のことへのフィードバックなのか返って逆効果になる場合があります。
育成は自分の成長につながる
「教える」ができるようになるには、自分が「理解」していないとできません。育成という行動は自分の成長にも大きく繋がります。「他の人に教えるのは面倒…」というメンバーもいたりしましたが、成長のチャンスを逃すよな…と思いました。確かに、育成には明確な答えがあるわけではなく、なかなかうまくいかないと歯がゆいときもあると思います。でも、次世代に繋ぐ為には、必ずやっていかなければならないことですので、その立場にいらっしゃる方は、大変かとは思いますが、自分のさらなる成長も含めて頑張っていただけたらと思います。
さいごに
最後まで読んでいただきありがとうございました。月並みな内容ばかりだったかもしれませんが、コメントやお問い合わせはお気軽にいただけたらと思います。もし共感いただけましたら、おすすめ商品のクリック・ご購入や寄付もご検討いただけるととても励みになります。よかったらお願いいたします。
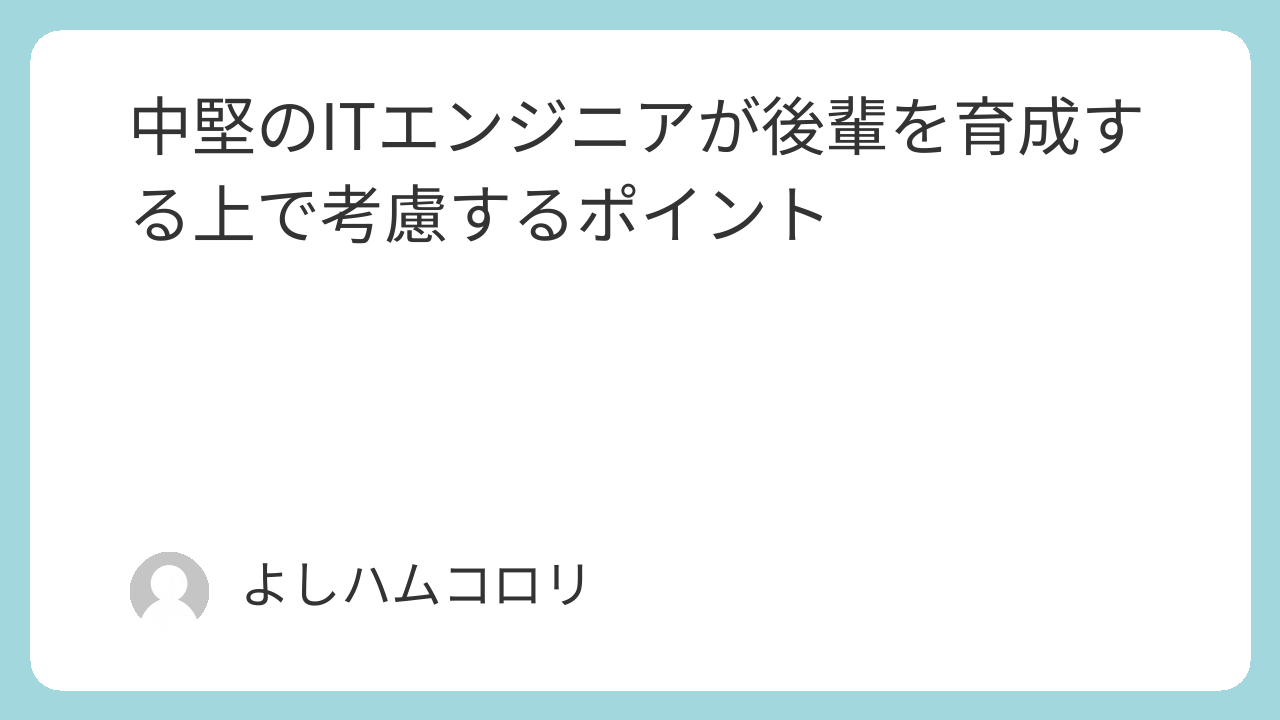





コメント